この記事は前回の記事
→村上春樹『スプートニックの恋人』にんじんと犬/交代する主人公【考察】
からの続きです
すみれの帰還は夢か幻か
物語の最後、すみれが前触れもなく帰ってくる。
唐突なこの展開は、現実のことなのか。
どうしてそんな結末がありえるのか?
考察してみる。
物語の最後「16」の章でのこと、ぼくは失踪したすみれの行方はわからないまま日本に帰って来ている。
日曜日の明け方(午前3時すぎ)、「ぼく」は目を覚まして枕元の電話機を眺める。
それは以前「2」の章で、同様の時間帯に「すみれ」から電話が掛かってきた電話機だ。
ぼくは、電話ボックスの中から自分に電話を掛けるすみれの姿を想像する。
その姿は、「髪はくしゃくしゃで、サイズの大きすぎる男物のヘリンボーンのジャケットを着て、左右ちがった靴下をはいている」。
これは「2」で変化する前のすみれのすがただ。
「彼女の頭の中にはぼくに話さなくてはならないことが詰まっている。朝までかかってもしゃべりきれないかもしれない。たとえば象徴と記号の違いについて」とぼくは思う。
すると「本当に電話のベルが鳴りだす。相手はすみれである。
「血のにじむような苦労をして、いろんなものをいっぱい乗り継いで、ここまで」帰ってきたとすみれは言う。
彼女は、どこかわからない「古典的な電話ボックス」の中にいて、その電話ボックスは「たぶんけっこう近く」にあって、「まっ四角」で、「交換可能で、あくまで記号的な電話ボックス」だという。
「君にとても会いたかった」とぼくが言うと、すみれも「わたしもあなたに会いたかった」と返す。
わたしにはあなたが本当に必要なんだって。あなたはわたし自身であり、わたしはあなた自身なんだって。ねぇ、わたしはどこかで――どこかわけのわからないところで――何かの喉を切ったんだと思う。包丁を研いで、石の心をもって。中国の門をつくるときのように、象徴的に。
最後に「ここに迎えにきて」とすみれが言って、電話は切れる。
このすみれの帰還については、現実なのかぼくの夢や想像なのか、意見が別れるところだ。
すみれからかかってきた電話の意味
「ここに迎えに来て」という最後の会話のなかで、よくわからない部分がある。
それは「象徴と記号の違い」や「電話ボックス」、「交換可能」という意味深な言葉だ。
おそらくこれらは、「2」の章におけるすみれとの電話を踏まえている。
作品の冒頭、すみれは従姉の結婚式で「ミュウ」と出会い、恋に落ちた。
「2」では、すみれからぼくに電話がかかってくる。
それは、結婚式のちょうど二週間後の日曜日の夜明け前(4時15分ごろ)のことで、すみれは「公園の近くの公衆電話」からぼくに電話をかけてきた。
そこですみれはぼくに、「記号と象徴のちがいってなあに?」と質問した。
この「記号と象徴」の違いを、ぼくは「天皇は日本国の象徴だ」というたとえを用いて説明する。
「天皇は日本国の象徴だ。しかしそれは天皇と日本国とが等価であることを意味するのではない。わかる?」
「わからない」
「いいかい、つまり矢印は一方通行なんだ。天皇は日本国の象徴であるけれど、日本国は天皇の象徴ではない」
説明を聞いたすみれは、あなたは説明するのが上手だ、とぼくをほめ、「あなたってきっと良い先生なのね」と言う。
そしてまた、「どうしてイカの足は十本で、八本じゃないの?」と質問する。この質問にぼくは「もう眠っていいかな? ぼくはほんとうに疲れているんだ。」と会話を打ち切ろうとする。
そこで、すみれはミュウという女性に恋に落ちたことを打ち明ける。
そんな流れだった。
実はこの会話は、ぼくにとって、”ぼくが恋していたすみれ”と話した最後の会話だった。
なぜなら次にぼくがすみれと顔を合わせた時、彼女の姿は大きく変化していたからだ。
次に会ったとき、すみれは、髪はショートカットで、ネイビーブルーの半袖のワンピースに薄いカーディガンを羽織り、中くらいの高さの黒いエナメルのヒール、そしてストッキングをはくようになっていた。
それは、くしゃくしゃの髪に、ぶかぶかのツィードのジャケットを着て、左右ちがう靴下を履いていた彼女とは異なる「スタイルを一新し」、「美しく洗練され」た姿だった。ぼくの目にも、「しっくりなじんでいた」と思えるほど。
ぼくにミュウへの恋心を打ち明けたあと、すみれは目に見えて変わってしまった。
このすみれの変化は、ぼくとしては好ましくなかった。
なぜならぼくが好きだったのは「以前のとんでもないかっこうのすみれの方」だから。
結末部、「16」の章のぼくが想像するすみれが「髪はくしゃくしゃで、サイズの大きすぎる男物のヘリンボーンのジャケットを着て、左右ちがった靴下をはいている」のも、それがミュウに恋する以前の、ぼくが恋をしたすみれの姿だからだ。
記号と電話ボックス
「16」の章ですみれが電話をかけてきた場所は、「電話ボックス」の中だった。
これは、「2」の章での公衆電話からかかってきたのおなじ状況だ。
しかし今回は「まっ四角な電話ボックス」であるとすみれは発言している。
「まっ四角」という表現は、「2」の章ではなかったものだ。この表現はどこから来ているか。
じつは、おなじ「真四角」という表現がされている場所がひとつある。
それは、ギリシャのすみれの部屋だ。
消える直前、すみれは「自分の部屋に戻る、しばらく一人になりたい」と言ってミュウの部屋を出ていった。
つまり、すみれはギリシャの自分の部屋で姿を消したことになる。
そして、そのギリシャのすみれの部屋について、ぼくは「まるで大きなさいころみたいな、飾りのない真四角な部屋だった」と述べている。
すみれが消えた場所であるギリシャの部屋と、
すみれが帰ってきた場所である電話ボックス。
両者は「真四角」、「まっ四角」という共通した単語によって記述されている。
これが、ただの偶然であるとは考えにくい。しかも、微妙に表記を変えているのも意図を感じさせる。
「16」ですみれは、電話ボックスについて「記号的」という言葉を用いている。
自分のいる場所がどこかわからない、「あくまで記号的な電話ボックス」、「すべてはあまりにも記号的だ」と彼女は述べる。
先ほど書いたぼくによる「天皇は日本国の象徴である」という説明によれば、
「記号」とは「交換可能」ということであり、
「象徴」とは「交換不可能」であることを表している。
電話ボックスが「まっ四角」で「記号的」ということは、「交換可能な」存在である。
そして、それと類似した「真四角な」ギリシャの部屋。
両者は、「真四角」という共通した言葉により、交換可能な場所なのではないか。
交換可能ということは?
「真四角なギリシャの部屋」と日本の「まっ四角な電話ボックス」とが、すみれと最後に交わした「記号」という言葉によって入口と出口のように、ひとつにつながった「通路」となったのではないか。あるいは、両者の場所が交換できるのではないか。
その流れがあるから、ぼくはなぜという疑問もなく、「迎えに行くよ」とすみれに言える。
象徴と中国の門の話
帰ってきたすみれは、「どこかで何かの喉を切ったんだと思う」、「中国の門をつくるときのように、象徴的に。」とぼくに言った。
「中国の門」とは、「1」の章でぼくがすみれに小説を書くことの比喩として語った中国の門のことだ。
「1」の章でぼくは次のように語っていた。
中国では、門には街の魂のようなものが宿っていると考えられていた。人々は古戦場から白骨を集めてきて、門をつくる時にはその骨を塗り込んでつくった。そこに犬を何匹か連れてきて、その「喉を短剣で切っ」て、血を門にかけた。そうすることでまだ温かい血とひからびた骨とが混じりあい、「古い魂は呪術的な力を身につける」のだと。小説を書く時も同様で、「本当の物語にはこっち側とあっち側を結びつけるための、呪術的な洗礼が必要とされる」。
なんだかよくわからない話だが、「16」ではすみれが、「何かの喉を切ったんだと思う。[中略]中国の門をつくるときのように、象徴的に。」と言う。
辞書で「呪術」という言葉を引くと、
「神仏に祈ったり口で何かを唱えたりして、超自然的な現象を起こさせる術。」とある。
つまり、呪術とは「自然現象では説明のつかない現象を起こさせる力」なのだ。
「何かの喉を切っ」たことで、物語は、消えたはずのすみれが帰還するという自然現象では説明のつかない展開を見せる。
「何かの喉を切る」の何かとは?
「ガールフレンド」との別れ、つまり「にんじん」との別れではないか。
記号と象徴、つまり犬(にんじん)とすみれ
以前の記事で、ぼくの中でにんじんが犬的な存在になっていると書いた。
しかし両者は、ぼくとの別れ方がちがう。
犬は不慮の事故で死んだが、にんじんは、ぼく自身の決断によって(ガールフレンドと別れるという形で)、関係が途絶えている。
にんじんとの関係は、ぼくの身の振り方によっては関係を持続させることもできた。
しかし、ぼくは「いろんな人のために」、「問題の一部になるわけにはいかない」として、ガールフレンドと別れにんじんと会うことはなくなる。
ただこれは嘘だ。ぼくがにんじんと別れたのは、すみれのためだった。
これは「いろんな人ではなく、すみれのことだけだった」とぼくは語ったことからもわかる。
ぼくにとってすみれは、にんじんや犬とはちがう「かけがえのない」存在だったのだ。
「わたしはどこかで――どこかわけのわからないところで――何かの喉を切ったんだと思う。包丁を研いで、石の心をもって。中国の門をつくるときのように、象徴的に。」というセリフ。
このなかにも「象徴的」という言葉が用いられている。
先ほど「記号と象徴のちがい」について、「記号」は交換可能、「象徴」とは交換不可能なことを示していると述べた。
「犬」は「にんじん」という存在に、とって代わることできる。
つまりぼくにとって犬やにんじんは記号的存在、交換できる存在といえる。
しかし、「14」でギリシャからの帰国の途に就いたぼくは、すみれが自分にとって「どれほど大事な、かけがえのない存在であったかということ」をあらためて理解した、とある。
ぼくはすみれと「自然に心をかさねあわせることができ」、「お互いの裸体を晒しあうように、それぞれの心を開いて見せあうことができた」と。
「かけがえのない存在」
「かけがえのない」つまり、それに代わる物が他にない存在。
すみれは、言葉通りの交換不可能な存在=象徴的存在と位置付けられるのだ。
記号的存在と象徴的存在、この点で犬(にんじん)とすみれは異なっている。
「2」の章でぼくとすみれは,「象徴」についてこんな会話をした。
「天皇は日本国の象徴だ。しかしそれは天皇と日本国とが等価であることを意味するのではない。わかる?」
「わからない」
「いいかい、つまり矢印は一方通行なんだ。天皇は日本国の象徴であるけれど、日本国は天皇の象徴ではない」
「象徴」とは「一方通行」、
「記号」とは「相互通行」でもあるとのこと。
これを考慮して、考えてみよう。
「相互通行」な「記号」は、ぼくと犬やにんじんの関係。
これは、気持ちが「通じあう」という表現ともつながる。
「一方通行」な「象徴」は、ぼくのすみれへの片思い。
ぼくはこれまで、引っ越しの時のようにすみれに対し強い性欲を感じても、その思いを禁欲的に抑えてきた。
ミュウに恋をしたとすみれに打ち明けられた時も、「ぼくに、じゃないよね?」と、冗談ぽく気持ちを暗に吐露するくらいだ。
すみれが自分の気持ちを「受け入れて」はくれないだろうこともぼくは悟っている。
一方通行の恋、片思い。
ぼくからすみれへの恋愛感情は一方的な関係であり、なおかつ交換不可能という、二つの意味で「象徴的」といえる。
「にんじん」の喉を切る
ガールフレンドと別れたぼくは、その足でアパートに帰り、シャワーを浴びる。
その時、自分の手に「命あるものを力まかせに切断してしまったようななまなましい感触が残っていた」と感じている。
ぼくにとって、気持ちの通じあえる相手となったはずのにんじんとの関係を、自らの手で切る。
その感覚は、犬の喉を切る、という表現と通じ合っている。
中国の門の比喩になぞらえれば、すみれは「古い魂」であり、ぼくがにんじんという「自前の犬」の喉を切ることで、その血によって呪術的な力を身につける。
つまりぼくは、自分にとって交換不可能な存在(すみれ)のために、にんじんとの関係を断ち、その代わりに、「血のにじむような苦労をして、いろんなものをいっぱい乗り継いで」すみれが帰ってくるという自然現象では説明のつかない象徴的な結末を、形作ったのではないか。
振り返ってみれば、すみれの消失という出来事は、本作の向かうべき結末を決定づけたと言っていい。
架空のギリシャの島という舞台が用意され、そこですみれが超自然的に忽然と消える。消失は読者に帰還を予感させる。どこかですみれは戻って来なくてはならない。そうでなければ終わることができない。
ぼくがにんじんとの関係と縁を切ることは、すみれが帰ってくるという呪術的な(超自然的な)結末を導くための重要な儀式のようなものだ。
ぼくと別れたあとのにんじん
ぼくが関係を断ったあと、にんじんはどうなるか。
ようやく、ぼくという気持ちの通じ合える存在を知ることができたにんじんは、二度と万引き事件は起こさないだろう。
しかし、ぼくとの別れによって彼は、犬を失ったぼくのように、その成長の過程で「うまく受け入れてくれる」誰かを探し当てなくてはいけなくなった。
つまりにんじんは、すみれへの片思いをつのらせるぼくとおなじく、相手に「受け入れてもらえない」という感情に苦しむのではないか。
にんじんとぼくの関係性は、そんなにんじんの未来をもまた予感させている。
まとめ
「ここに迎えに来て」という最後の会話のなかで、意味深だった
・「象徴と記号の違い」
・「電話ボックス」
・「交換可能」
という言葉について考察し。
・記号とは、犬やにんじんのような交換可能な存在。
・象徴とは、逆に交換不可能な存在。ぼくにとってのすみれ
・中国の門の比喩になぞらえ、ぼくにとって犬的な存在となったにんじんの関係を自ら断つという儀式を行い、すみれの帰還という超自然的な展開へと繋がったのではないか。
・すみれは「真四角」という表現で共通する記号的つまり存在が交換可能な「ギリシャの部屋」と「電話ボックス」を通して帰還したのではないか
という妄想をした。

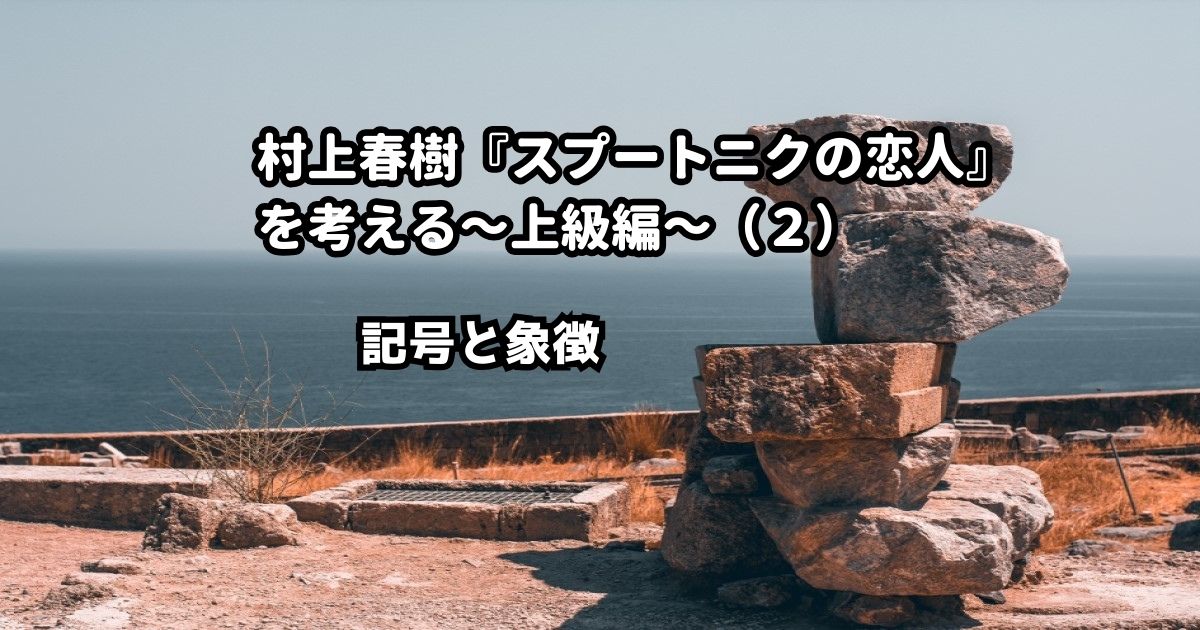

コメント